現代の高度な情報社会において、日本の文化的背景を反映しながらも、処理しやすく、運用しやすい年号があれば──
システム屋も、ユーザーも、そして未来のメンテナたちも、もう少し平和になれるのでは? そんな発想から私は「上皇紀」という新しい紀年法の導入を提案するゾイ
🗓 上皇紀とは何か?
「上皇紀」は、1989年(平成元年)=上皇紀元年として定義する暦です。
この年は、平成天皇(現・上皇陛下)が即位された年であり、日本が冷戦後の平和と国際協調の時代に踏み出した象徴的なタイミングでもあります。
つまり、令和6年(2024年)は上皇紀35年にあたります。
🎌 名目と本音
もちろん、平和の象徴とか、国際関係の発展とか、そういう「名目」はあとづけです。
本音を言えば「元号の処理、マジでだるい」。
でも、「じゃあ皇紀で一本化しよう」と言えば今度は政治色や歴史観の問題が立ちはだかる。(アホなネトウヨ扱いされるのダルい)
素直に西暦だけでいいと思っても、「日本のものを使うべきだろ地産地消JK(常識的に考えて)」からチクリと言われることもある。
だったら、皇紀でも元号でも西暦でもない「日本の年号」を作ってしまえばいいじゃないか──
というのが上皇紀の出発点ゾイ。
🔧 元号をシステムに入れるという地獄
少し技術的な話をします。
一般的な業務システムでは、元号が絡むと以下のような作業が必要になります:
- 元号マスタの設計・メンテナンス(改元日、略称、表示名など)
- 和暦⇔西暦の変換クラス・共通関数の実装
- 改元境界での例外処理、UI対応
- 「M」「T」「S」「H」「R」などイニシャルの衝突リスク
- 急な改元発表でテスト計画やリリース計画が崩壊する可能性
改元があるたびに、保守・改修・説明・問い合わせ対応の人月が飛ぶ。
開発者もPMもユーザーも疲弊する。
✅ 上皇紀の利点(実務的なやつ)
- 定数換算のみで西暦と連携可能(1989年 = 上皇紀元年)
- マスタ管理不要・変換不要・改元なし
- 境界エラーや仕様書ミスの原因を根本から排除
- 将来的にGitHub等での民主的な更新・提案プロセスも構想中
- 政治色・宗教色を薄めつつ、”日本らしさ” を維持できる
「日付変換に悩まなくていい」だけでどれほど気が楽になるか、これは元号地獄を知ってる人はわかるよな?(脅し
📢 上皇紀を広めるには?
この暦は、まず日常的な使い方から始めるのがベストです。
- メモや手帳に「上皇紀35年8月2日」と書いてみる
- SNSや技術記事で「2024年(上皇紀35年)」と併記する
- リリースノートや個人プロジェクトのバージョン管理に使ってみる
すると、だんだんこう思えてきます:
……あれ? これ、案外使いやすくない?
🧠 補助暦としての可能性
上皇紀は、和暦のように頻繁に変わらず、西暦のように宗教起源でもない。
その中間で、日本発の中立的な補助暦として、教育・市民運動・ドキュメント・技術系用途など、多分野に展開できるポテンシャルを持っている。
🔚 終わりに
上皇紀はジョークのようでいて、本質的には極めて実務的な提案(と思っている
「暦はただの日付の表記方法」と思うかもしれませんが、その選択一つで、我々の仕事量も心の平穏も、ずいぶん変わってくるのです。
日本の文化を尊重しながら、合理的で、誰にでも使いやすい。
そんな「第4の暦」として、上皇紀、そろそろ試してみませんか?
(年変わるたびにバッチ処理不安になる俺さまより)
この記事は過去記事をより丁寧に、ブラッシュアップという名のAI(ChatGPT君、愛称はチャッピー)との共著です

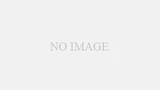
コメント